「体のしくみとはたらき」#0 はじめに
- 2025.03.16
- 新連載! 体のしくみとはたらき

体がバラバラにならずに、心身がかみあって働いてくれたら。
いつの間にか自動運転が身についた体に、1分間だけ注意を向けることは、変化のきっかけとなります。
無意識化されたパターンを編み直すチャンスが与えられるからです。
では、何に注意を向けたらいいのか。
どのように注意を払ったらいいのか。
実際にやってみましょう。
そして、別々にとらえがちな心と体が、もとは一つであることをお話ししたいと思います。
頭の中は同時にあれこれ考えますが、体はつねに目の前にあって、五感を使って環境とやりとりしています。「今ここ」に注意を払い、自分の感覚とのつながりを保つことで、リラックス、パワー、集中、ひらめきをもたらすことができます。
一番簡単でオススメな実践のひとつは、耳を澄ますこと。
次のオススメで効果がわかりやすいのは、呼吸に意識を向けることです。
聴こえてくる音も、自分の呼吸も、いきなり判断や評価をせずに、新しい友人のように様子をみてみましょう。1分間だけ、静けさを保ちます。
静けさを求めるのは、新しい友人にではなく、自分自身に、です。
どんなにうるさくても、どんなおかしな呼吸でも、意識を向けた友人の隣に、静かに座ります。
それが、あなたの無意識の隣に、あなたの意識が座った瞬間です。
何も押し付けられないので、無意識は安心します。すぐに、場の静けさや呼吸の深まりに気づくでしょう。
症状も、無意識の領域から生じます。病気になりたがる人は、あまりいません。
体はつながりを失うと、文字通り細胞レベルでも力を失い、バラバラになっていきます。
死が訪れると、それらは分解されます。しかしそれは元の世界への帰還かもしれません。
つながりのある世界、体の中の不思議についての話をはじめましょう。
体の中にはいくつかの内臓器官が埋まっていて、お互いに情報や物質の交換をしながら働いてくれています。そのしくみを「器官系(システム)」と呼びます。器官系ごとに、目次を立てます。
- 外皮系(環境感知と保護)
- 感覚系(感じる)
- 神経系(情報コントロール、思考)
- 内分泌系、細胞(調節、伝達)
- 呼吸器系(エネルギー、ATP、自己表現)
- 消化器系、代謝系(食べる、合成する)
- 循環器系:心臓血管系とリンパ系(運搬、リズム)
- 免疫系(守る、教育する)
- 泌尿器系(捨てる)
- 骨格系(支える)
- 筋系(動く)
- 生殖器系(官能性、性的特質、子孫を残す)
わたしたちは通常、これらの器官系がうまく機能してくれるかどうかを気にします。
体の「機能」は、「構造」に依存します。「構造」+「機能」を学ぶのが「解剖生理学」です。
器官系の構造、つまり内臓器官の形や関係性は、エネルギーによって決まります。一般的な解剖生理学では、食べ物から取り出すATP(アデノシン三リン酸)が細胞にエネルギー供給すると説明します。
しかし体のエネルギーはATPだけではありません。光、音、意識もエネルギーです。何十兆個もある体内のすべての細胞はつねに振動していて、その組み合わせで器官の形を編み出しています。
詳しくは次の記事で書きますが、例えば、外皮系(皮膚や髪、爪など)の「しくみ」は、大きく二つの役割を果たすためにあります。
①環境感知と応答
②保護
動物が持っている外皮系の知性は、なんといっても「自分の体と自分の体以外を区別できる」ことから始まります。
体の「はたらき」というと、機械のように機能することを思い浮かべがちですが、意識のはたらき、知性のはたらきこそが、構造を制御し、機能を決める大きなエネルギーなのです。
こうした観点から外皮系の「はたらき」をとらえようとした時、外皮系のもつ意識をいくつか挙げることができます。
①自分の体をもつ
②環境から人生を吸い込む
③皮膚や髪の官能性、感受性
④生存に関わる恐れの感情を皮膚に抱く(罪悪感や不安)
体の器官系がそれぞれ持っている「はたらく意識」は、体を構成する四つの要素に働きかけます。
①気
②熱
③血
④水
そして、「この四要素」の兼ね合いで、体質や気質、症状が表に出てきます。
「体のしくみとはたらき」は、以上のようなキーワードを使って、どのように心身がつながっているか器官系ごとに描き出そうとするものです。
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
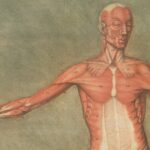
「体のしくみとはたらき」 #1 外皮系 – 乾燥した皮膚 2025.03.19